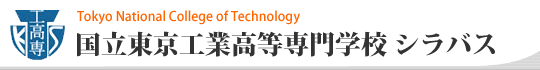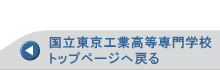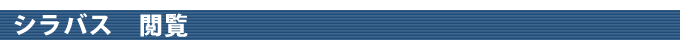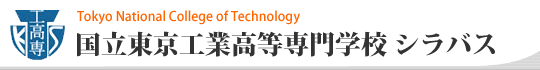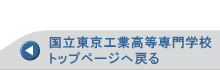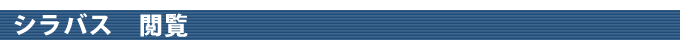| 特別研究指導教員の研究室に所属して2年間研究を行う。各教員のテーマ概要を以下に示す。 |
|
| ・高橋三男 「チタンの陽極酸化によるナノポーラス作製とインプラント応用に関する研究」:チタンは、優れた |
| 移植片材料といえる。しかし、チタンの表面形態は、細胞付着に大きな影響を及ぼすため、チタン表面にナノポーラ |
| スを形成し、インプラントの応用に役立てることを目指している。 |
|
| ・北折典之 「ステンレススチールの溶接に伴うスケールの除去剤に関する研究」:現在、スケール除去剤としてフ |
| ッ |
| 素酸と硝酸の混合溶液が使用されている。この除去剤を環境に与える影響の少ない薬液に置き換えることを目指す。 |
|
| ・石井宏幸 「気固系反応装置における流動化特性に関する研究」:気固系反応装置の中でも流動層が用いられて |
| いるものとして廃棄物燃焼装置を対象とし、ダイオキシン対策、農産・畜産廃棄物燃焼の課題解決の為に層内流動化 |
| 状態の把握及び、その制御方法を検討する。 |
|
| ・町田 茂 「有機材料の機能化の研究」:有機化合物の電子状態や分子間相互作用に着目して機能発現が期待され |
| る分子構造を設計して合成を行う。また、得られた化合物の物性を評価して、効率の高い電子デバイスや光デバイス |
| の実現を目指す。 |
|
| ・土屋賢一 「コンピュータシミュレーションによる固体内不純物の挙動解析」:金属中の水素の挙動を量子力学 |
| 的に解析し水素の安定位置や拡散経路について推測する。また、水素吸蔵の限界について予測を行う。その結果を燃 |
| 料電池等の開発に役立てる。 |
|
| ・庄司 良 「バイオアッセイによる環境管理手法の確立」:新しい環境管理手法として注目されているバイオ |
| アッセイを如何に利用していくべきかについて、有害性評価,削減、予測など様々なアプローチから研究する。 |
|
| ・中川 修 「構造の制御された高分子の合成」:高分子化合物は化学構造が同じであっても、その立体構造が |
| 異なれば違った物性を示すことが多い。主にリビングアニオン重合法を用いて、立体構造の制御された高分子を |
| 合成し、構造と物性の関係を調べる。 |
|
| ・城石英伸 「燃料電池の要素研究と物質吸着の分光学的研究」:燃料電池の触媒や膜などの要素について、評価方法 |
| を学習するとともに、燃料電池材料の開発を行う。また、界面への物質吸着を分光学的手法を使って研究し、新しい |
| デバイスを開発することを目指す。 |
|
| ・伊藤篤子 「細胞骨格の機能・構造解析」:細胞骨格は原始的生物から高等生物まで共通点が多い。海産無脊椎 |
| 動物を中心に、アクチン、ミオシン、トロポミオシン、トロポニンといった細胞骨格タンパク質の挙動を生化学的・ |
| 分子生物学的に解析し、その機能・構造を明らかにする。 |
|