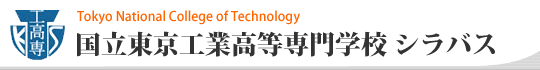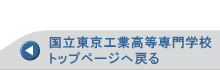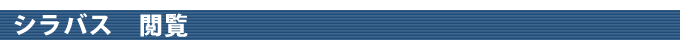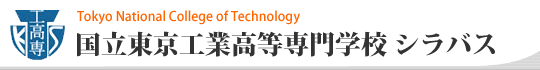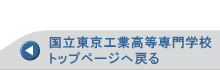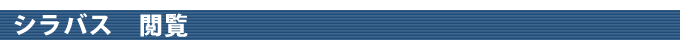| 授業の目標と概要 |
| 建物内の移動などで活用するための乾電池で室内走行ができる超小型電気自動車を製作することを想定し,これに |
| 使用するギアボックスの設計・製図・製作・評価をする。従来の設計・製図の授業の目標である「機械要素における |
| 最適な選択方法とその図面化」などを学ぶことに加え,本授業では,設計・製図・製作・評価の流れの中で設計・製 |
| 図を学習することにより,創造性を高め,イノベーションを意識したものづくりを意識する契機とする。また,設計 |
| 内容など討論を通して,ディベート力・コミュニュケーション力も高める。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| ・機械工学科の3本柱のうちの「ものづくり工学系科目群」の一つである。 |
| ・2年で学習した「基礎製図」のスキルを確実なものとする共に,ものづくりの一連のプロセスを学習する。 |
| ・本授業で得た知識については「機械設計法A」,「機械設計法B」,「基礎機械要素」,「基礎材料力学A」およ |
| び「基礎材料力学B」などでさらに知識を深めることとなる。 |
|
| 授業の内容 |
| 第1回 課題に取り組むにあたり必要な知識の習得 |
| ・動力伝達 |
| ・段付歯車装置の減速比 |
| ・歯車および軸の強度計算 |
| ・モータ特性 |
| 第2回 仕様作成 |
| ・グループ討論を行い,仕様を決定する。 |
| 第3回〜第4回 設計(個人作業) |
| ・決定した仕様を元に設計を行い,設計書を作成する。 |
| 第5回〜第6回 組立図の製図(個人作業) |
| ・設計書に基づき組立図を作成する。 |
| 第7回〜第8回 部品図の製図(個人作業) |
| ・各歯車およびその他の部品を製図する。 |
| 第9回 製作するギアボックスの図面の決定(グループ作業) |
| ・各自の設計書および図面を資料として、どの設計が最適か討論を行い,製作する設計書および図面を決定する。 |
| 第10〜第14回 ギアボックスの製作・性能評価(グループ作業) |
| 決定した設計書および図面に基づきギアボックスを製作し超小型車にとりつけ性能評価などを行う。 |
| 第15回 設計内容の評価・議論・発表 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 教科書 |
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
プロセスが重要な教科である。積極的に課題に取り組むこと。
設計中に不明な個所が出てきたら、自学自習により知識を補うこと。
|
|
| 評価基準 |
|
・提出物を全て提出しなければ評価しない。
・提出物および取組で評価する。また、図面の「丁寧さ」「正確さ」は評価に大きく影響する。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|