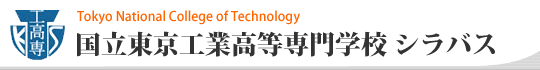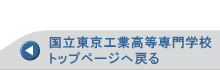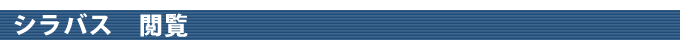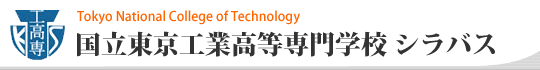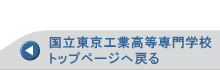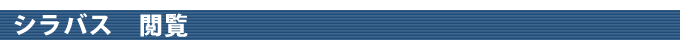| 授業の目標と概要 |
| 触媒とは物と物との間をとりもちそれらの反応を容易にするのに重要な役割を果たすものである。言い換えると、化 |
| 学反応の速度を著しく促進するが、反応の前後で自らは変化しない物質である。本授業では、化学工学上重要である |
| 触媒に関して、その歴史、基礎およびその応用例を学ぶ。加えて、現在注目を集めている光触媒についても学習す |
| る。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 触媒は、化学反応速度を制御することから工学を学ぶ上で重要なテーマである。また、環境を守る点からも重要であ |
| る。化学の基礎を学んできた4年次後期に行うことは、学ぶ上でも理解しやすい。化学の新しい工業的応用例をエネ |
| ルギー、環境、製造コストの面から学習する。 |
|
|
|
| 1.触媒とは(触媒の定義) |
2 |
| ・一般的な触媒の役割定義に関して学習する。 |
|
| 2.触媒の発見とその歴史 |
2 |
| ・触媒の歴史と触媒の発展に関して学習する。 |
|
| 3.触媒反応プロセス |
2 |
| ・触媒の寿命と生産性を考慮した交換サイクルに関して学習する。 |
|
| 4.工業的な代表的応用例 |
2 |
| ・工業化されているいくつかの代表例を解説し、触媒の役割を理解する。 |
|
| 5.触媒のデザインと調整 |
2 |
| ・新規な反応触媒を開発する際の考え方に関して学習する。 |
|
| 6.コスト試算 |
4 |
| ・各自で、コストと生産の理想的な関係を学習する。 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 7.環境触媒(自動車触媒) |
2 |
| ・ガソリンエンジン用三元触媒について学習する。 |
|
| 8.光触媒 |
12 |
| (1)光触媒の発見と歴史 |
|
| ・環境の面で、エネルギーの面で、現在最も注力されている光触媒に関して理解する。 |
|
| ・光触媒が発見されるまでの過程、日本のおかれているエネルギー事情。 |
|
| (2)光触媒反応が進むしくみ(本多・藤嶋効果) |
|
| ・基本的な光触媒の原理、反応のしくみに関して学習する。ホンダ・フジシマ効果を理解する。 |
|
| (3)酸化チタンの特長 |
|
| ・光触媒の代表例である酸化チタンの結晶構造と特長を学習する。 |
|
| (4)いろいろな光触媒 |
|
| ・酸化チタン以外の光触媒効果を発現する半導体について学習する。 |
|
| (5)光触媒の応用例 |
|
| ・超親水効果、有機物の分解など、光触媒の実用的な応用例を理論的学ぶ。 |
|
|
|
|
|
|