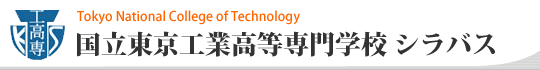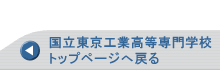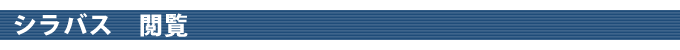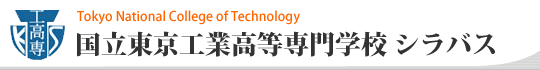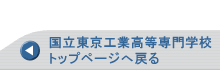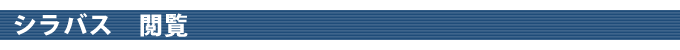| 授業の目標と概要 |
| 具体的なケースを材料に、経営学の基本的な考え方を学び、現実の経営現象を理解する力を身につけることを目指す。 |
| ケースに関わる課題を授業中に発表してもらう。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 本科の社会系科目としては、カリキュラムの最後に位置する。 |
|
|
|
| 1.はじめに |
2 |
| 授業の目的等を確認する。 |
|
|
|
| 2.企業の基本 |
8 |
| 企業の形態、特に株式会社の機能と構造を考える(第1章、第2章)。 |
|
|
|
| 3.企業の歴史 |
4 |
| アメリカ自動車産業の経営史(フォードやGM)を取り上げながら、現代企業の形成過程と特徴を考える |
|
| (第4章)。 |
|
|
|
| 4.企業の競争戦略 |
4 |
| 日本のハンバーガー市場における主要企業2社(マックとモス)の競争戦略を考える(第6章)。 |
|
|
|
| 5.技術と経営 |
4 |
| 富士写真フィルムを事例に、技術と競争力の関係について考える(第9章)。 |
|
|
|
| 6.日本的経営の構造と変化 |
4 |
| 人事管理制度と生産システムの側面から、日本的経営の実態を考える(第11章、14章)。 |
|
|
|
| 7.企業統治 |
2 |
| カゴメを事例に、日本企業の支配構造の特徴とその変遷について考える(第17章)。 |
|
|
|
| 8.まとめ |
2 |
| 各自の設定したテーマについて、調査、ディスカッションの上、小論文作成の準備をする。 |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| 教科書 |
|
谷口明丈ほか『ケースに学ぶ経営学』(新版)有斐閣、2008年。
|
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
授業中に出される課題は必ず提出すること(課題を提出しない者は小論文を提出する権利を失う)。
|
|
| 評価基準 |
|
1.企業に関する基本的制度・理論を理解し、説明できること。2.適切な資料をもとに課題レポートや小論文を作成できること。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|