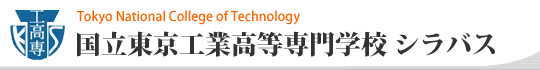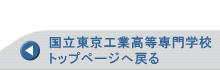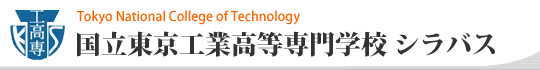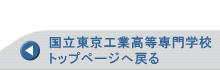| 犯罪の被害者に対する法的支援の仕組などについて解説する。 |
|
| 14 知的財産法、情報と法 |
2 |
| 知的財産法の保護対象と救済手段について概説する。情報をめぐるさまざまな法規制について説明する。 |
|
|
|
|
|
| 《続き・授業の目標と概要》 |
|
| さらに、社会に対する洞察を深めるという見地から、刑事法に関わる分野について掘り下げて扱う。将来、 |
|
| 工業専門職に従事した場合には、特別の法律知識を要することになるが、それらをただ断片的に覚え込むだけ |
|
| では、実際に役立つことが少ない。問題を法律的に筋道立てて考え、実用する力を身につけるためには、まず |
|
| もって基本的な法律知識を正確に習得し、法律解釈の基礎をしっかりと理解することが肝要である。 |
|
| |
|
| 《履修上の注意》 |
|
| 必要な基礎知識を覚えることは当然であるが、なぜそうなのかという理念や根拠も大事にして学習すること。 |
|
| わからないところは気軽に質問してほしい。法律の初学者であることを考慮して、具体的なイメージがわく |
|
| ように事例を用いて解説するが、法律解釈の話は、性質上、抽象的にならざるをえないことも確かである。わ |
|
| かりにくいと敬遠するのではなく、この機会に、物事を概念的・抽象的に思考することの面白さも追求してい |
|
| ただきたい。なお、授業の進度によっては、中間試験を課題レポートに代えることもある。 |
|