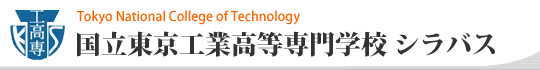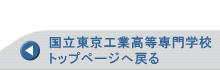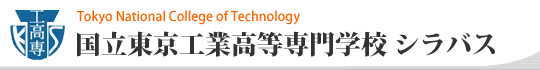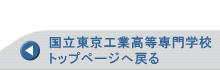| 授業の目標と概要 |
| 国際社会を舞台に活躍していく技術者にとって必要な人文学的教養を、日本とアジアの交流の歴史を学ぶ中で身につ |
| けていくことを目的とする。特に東アジア・東南アジア地域と日本との関わりについて歴史的事実を確認し、考える |
| べき問題について討議を重ねていく。その中から、アジアと日本とのこれからの関係についても考えを深めていく。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 日本史の発展型として,アジア史,世界史も視野に入れた国際的歴史的教養を広く深く学べる科目である.将来,と |
| りわけアジア各国で働いたり,アジアからのゲストと交際・交渉したりすることもあるだろう高専生にとって,本授 |
| 業などで国際的歴史的教養を補うことが有用である. |
|
|
|
| 1.ゼミの概要と目的について、アジアについて |
2 |
| 2.アジアの中の日本 |
2 |
| 3.アジアの中の日本(ゼミ生による討議) |
2 |
| 4.東アジアの諸地域と日本 |
2 |
| 5.東南アジアの諸地域と日本 |
2 |
| 6.モノとヒトの交流史①(前近代の東シナ海交易の視点から) |
2 |
| 7.モノとヒトの交流史②(「鉄砲伝来」の視点から) |
2 |
| 8.モノとヒトの交流史③(「ナマコ」の視点から) |
2 |
| 9.モノとヒトの交流史④(大日本帝国の視点から) |
2 |
| 10.私のアジア論Ⅰ(ゼミ生による報告) |
2 |
| 11.私のアジア論Ⅱ(同 上) |
2 |
| 12.私のアジア論Ⅲ(同 上) |
2 |
| 13.私のアジア論Ⅳ(同 上) |
2 |
| 14.アジアの日本の関係のこれから(主に中国、朝鮮半島との関わりを中心に) |
2 |
| 15.ゼミのまとめ |
2 |
| 16.学年末試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
自らの頭で考え、積極的にゼミに参加する姿勢が重要である。配布された文献のコピーやプリントには、ゼミの前に必ず目を通すようにしておくようにすること。レポート作成や研究発表の機会も積極的に設けていく予定。
|
|
| 評価基準 |
|
アジアと日本の交流の歴史について客観的な事実を習得する。それらを踏まえた上で、日本とアジアの将来的な関係について、自分なりの見識を持ち発信できるようにする。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|