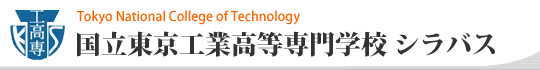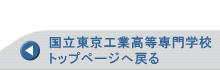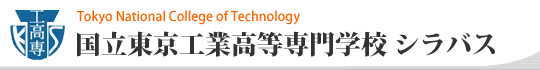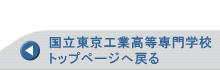| 授業の目標と概要 |
| 企業は、生産活動にとどまらず、現代社会において最も影響力のある組織のひとつになっている。多くの科学技術の成 |
| 果も、企業を通じて社会に提供される。また、受講生の多くは、今後、企業に職を得るだろう。本授業は、企業の発展 |
| 過程と現代社会における企業の位置づけを理解するものである。併せて、企業を題材に、考える、調べる、表現する |
| (書く、話す)等の汎用的な知的能力全体の向上を目指す。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 本科の社会系科目としては、カリキュラムの最後に位置する。これまでに学んだ知識やインターンシップでの経験を踏 |
| まえて取り組んでほしい。 |
|
|
|
| 1.はじめに |
1 |
| 授業の目的等を確認する。 |
|
|
|
| 2.企業の基本 |
3 |
| 会社の形態、とくに株式会社の機能と構造を考える。 |
|
|
|
| 3.企業の歴史 |
4 |
| アメリカ自動車産業の経営史(フォードやGM)を取り上げながら、現代企業の形成過程と特徴を考える。 |
|
|
|
| 4.企業の戦略と組織 |
6 |
| 企業戦略と競争戦略の基本及び戦略に適合した組織のあり方を考える。 |
|
|
|
| 5.日本的経営の構造と変化 |
6 |
| 人事管理制度と生産システムの側面から、日本的経営の実態を考える。 |
|
|
|
| 6.技術と経営 |
4 |
| 技術と競争力の関係、とくにコアコンピタンスとしての技術の活かし方を考える。 |
|
|
|
| 7.企業統治と企業倫理 |
4 |
| 三菱ふそう等を例に、企業の統治構造と社会的な存在でる企業の倫理性の問題を考える。 |
|
|
|
| 8.まとめ |
1 |
| 各自の設定したテーマについて、調査、ディスカッションのうえ、小論文作成の準備をする。 |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
谷口明丈ほか『ケースに学ぶ経営学』(新版)有斐閣、2008年。
|
|
| 補助教科書 |
|
授業中に指定する(教科書内にも指示されている)。また、講義レジュメを配布する。
|
|
| 履修上の注意 |
|
メディアは問わないが、信頼できるソースから継続的に情報を収集し、自分の言葉でまとめ考える習慣をつけること(就職等にも役立つ)。課題等は必ず提出すること(提出・受理が8割未満の学生は評価対象としない)。
|
|
| 評価基準 |
|
1.企業に関する基本的制度・理論を理解し、これを説明できること。2.適切な資料を収集・分析し、小論文等を作成できること。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|