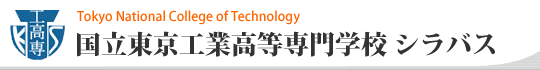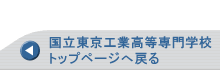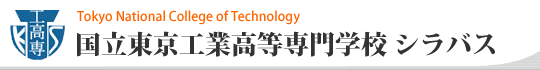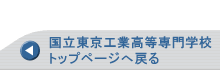| 授業の目標と概要 |
| 中小企業やベンチャー企業は、日本のものづくりを支えるのみならず、新たなビジネスの創出する原動力である。一 |
| 方で、少子高齢化の時代においては、職住近接型の雇用の創出、身近な商品やサービスの提供、地域における税収の |
| 確保等、多様な役割を期待される存在でもある。本授業では、基本事項を講義で考えながら、各自のテーマに従った |
| 調 |
| 査、ディスカッション、レポート作成を行っていく。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 本科の社会系科目や専攻科「技術者倫理」のみならず、「中小企業」を切り口にこれまでの学習内容を総合する内容 |
| で |
| ある。 |
|
|
|
| 1.はじめに |
1 |
| 授業の概要、進め方の説明、資料の紹介 |
|
|
3 |
| 2.中小企業とは何か |
|
| 法的概念規定、量的確認、特色を考える。 |
4 |
|
|
| 3.戦後日本における中小企業と中小企業政策 |
|
| 中小企業問題と中小企業政策の変遷を考える。 |
4 |
|
|
| 4.中小工業の存立状況 |
|
| 下請け、系列、産業集積等の観点から、ものづくりにおける中小企業の役割とその変化を考える。 |
2 |
|
|
| 5、中小商業の存立状況 |
6 |
| 小売業を中心に、商業における中小企業の役割とその変化を考える。 |
|
|
|
| 6、課題発表 |
10 |
| 指定された資料に基づき発表する。 |
|
|
|
| 7、調査、ディスカッション、レポート作成 |
|
| 講義や課題発表に基づきながら各自のテーマを設定し、調査、ディスカッション、レポート作成を行う。 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| 教科書 |
|
利用しない。なお、授業においてはレジュメ・資料を配布する。
|
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
課題や発表の確実な遂行はもちろん、質疑への積極的参加が義務である。
|
|
| 評価基準 |
|
適切な情報を収集するために具体的に行動できること。また、説得力をもって発表とレポート作成ができること(当然、「厳しい」質疑と批評にも耐えられること)。
|
|
| 評価法 |
|
レポートなど40%,発表と質疑40%,課題等20%
|
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|