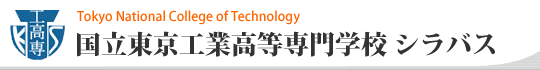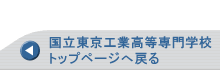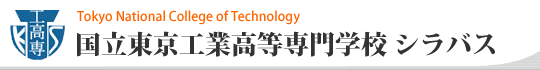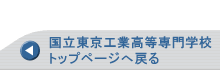| 1.実験の心得 |
| 実験室の利用、器具および試薬の取り扱いと基準、安全性留意、レポートの書き方、実験の進め方などを説明する。 |
| 2.実験講義 |
| 各実験テーマ内容についての講義する。 |
| 3.無機化学実験 |
| (実験テーマA,Bは全員行う。C,D,E,Fは、この中から2テーマを選択して行う。 |
| 実験テーマA: 電気メッキ(銅メッキ) |
| 銅の電気メッキを行い、ファラディーの法則を確認する。メッキ進行に伴う表面の変化も合わせて観察する。 |
| 実験テーマB: イオン交換樹脂によるイオン分離 |
| 陽イオン交換樹脂、陰イオン交換樹脂による銅イオンの交換反応およびNi、Fe、Coイオンの分離を行う。 |
| 実験テーマC: 食塩水の電気分解 |
| 食塩水の電気分解により次亜塩素酸ナトリウムを合成し、ヨウ素法によりその溶液の有効塩素濃度を定量分析する。 |
| 反応時間、濃度、電極材質の違いによる分解反応の進行を観察する。 |
| 自分で考え、新しい実験を2つ加える。 |
| 実験テーマD: 遷移金属錯体の合成と可視光スペクトルの測定 |
| コバルトと鉄の錯体を合成し、色の変化を確認するとともに、分光光度計により吸収スペクトルを測定し、発色の原 |
| 理を学習する。 |
| 尚、この実験では、発色等に関する考察を行えるような実験を加える。 |
| 実験テーマE: アルミニウムの原子量測定 |
| (1)ルツボの恒量(2)ろ紙の灰化(3)アルミニウムの原子量測定 |
| ・ルツボをガスバーナーで加熱、冷却後重さを測定する。恒量化するまで同じ操作を繰り返す。 |
| (恒量化の意味を学習) |
| ・ろ紙を焼却し(灰化)、その重量変化を調べる。 |
| ・水酸化アルミニウムの沈殿を恒量したルツボを用いて焼却し、酸化アルミニウムに変え、その重さの変化から |
| アルミニウムの原子量を求める。 |
| ・この実験では、重量分析法の課題について自分で計画し、追加実験を加える。 |
| 実験テーマF:電解によるアルマイトの作製とその特性評価 |
| 本実験では、酸性度の異なる溶液でアルミニウムを電解し生成されるアルマイト被膜の強度を比較するとともに、ア |
| ルマイト被膜の特徴を調べ、加えてこの技術を用いてアルミニウムの着色を試みる。 |
| 4.実験結果報告発表 |
| 今までに行ってきた無機化学実験の中から1人1テーマの発表とする。 |
| 発表時間は1人7分間。6分以下または8分以上となった場合、発表不十分として再発表となる。 |
|
|
|
|
| |