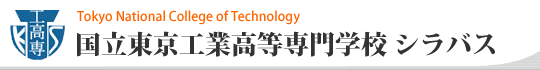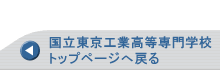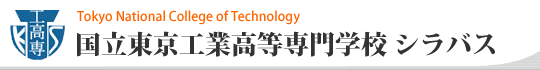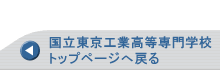| 授業の目標と概要 |
| 人間活動による環境への負荷を減らすための工学的な技術開発が進められている.本講義では,種々の環境問題の本質 |
| とその解決策について,講義と最新情報を交えて紹介し,環境工学の科学的理解と今後の技術者としての社会生活を送 |
| る上で不可欠な知識の取得をめざす。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 分析化学・化学工学・環境科学と関連しており、生物学的知見を加えて環境の保護・管理の面から学習する。 |
|
|
|
| 1. 授業ガイダンス |
2 |
| 2. 環境問題の量的・質的変遷 |
4 |
| 人口の動向,経済の発展,公害問題から地球環境問題への流れを理解する |
|
| 3.公害問題 |
4 |
| 原因と対策について,過去の教訓を踏まえて,現在の公害に対処する方策について考察する |
|
| 4.化学物質による健康被害 |
4 |
| 人間と環境のかかわりについて考察し,人間活動が環境汚染を引き起こし,逆に汚染された環境が人間活動 |
|
| に影響を与える構図を理解する.そしてその負のスパイラルを断ち切るためにどうしたらよいかについて,現 |
|
| 代科学がなしうる寄与について考察する. |
|
|
|
|
| 5.地域環境問題 |
6 |
| 公害問題と環境問題の全体の整理,酸性雨,水環境,リスク管理とリスク評価,土壌汚染,廃棄物など,一 |
|
| つ一つの地域環境問題について,その原因と対策について理解する. |
|
| 6.地球環境問題 |
4 |
| 地球温暖化問題,オゾンホールを題材にして,グローバルな環境問題について理解し,地域環境問題と地球 |
|
| 環境問題の質的・量的違いについて考察する. |
|
| 7.資源エネルギー問題 |
2 |
| 資源エネルギー問題は環境問題と密接に関係し,車の両輪のようにどちらかが回らないとどちらも両立しな |
|
| い切っても切れない関係にある.化石燃料代替エネルギー,燃料電池はその両方の問題を解決できる切り札た |
|
| りえるか? |
|
| 8.食糧問題 |
2 |
| 現代の食料生産はエネルギーを大量に消費する集約的な農業に基づくものであり,そもそもが環境問題の原 |
|
| 因となりうるし,資源エネルギーを大量に消費する.持続可能な社会の構築にあるべき食糧生産のあり方とは |
|
| どういったものであろうか? |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
各種科学技術と知見が中心であるが、常に種々の科学技術的な視点に基づく考察を施すようにする.
|
|
| 評価基準 |
|
定期試験(全評価の4分の3)と授業内提出物点(全評価の4分の1)100点満点に換算した合計点で評価する。60点以上を合格とする。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|