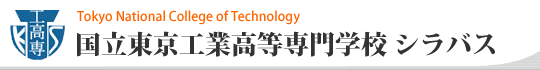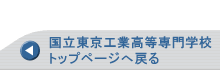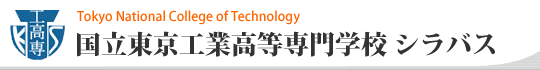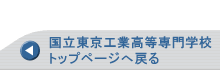| 授業の目標と概要 |
| 文化人類学とは異文化について知り、また自らの文化をも客観的な視点で問い直す学問である。授業では異文化を通 |
| じて自分の常識を問い直すための基礎概念や手法に触れつつ、文化人類学的視点の育成を目指す。今年のテーマは文 |
| 化人類学的視座から見た科学」とする。具体的には人類学者ブルーノ・ラトゥールの『科学が作られているとき』を |
| 分担して輪読し、発表する。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 本校に欠けている世界地理関連科目を学べる貴重な科目である。文化人類学の専門的知見を活用しながら、学生によ |
| る異文化理解に貢献できる。 |
|
|
|
| 第一回 ガイダンスと発表箇所決定 |
2 |
|
|
|
|
| 第二回 文化人類学とは何か |
2 |
|
|
|
|
| 第三・四回 文化人類学の方法論1.2 |
4 |
|
|
|
|
| 第五回 「もの」とわざの人類学 |
2 |
|
|
|
|
| 第六回 「科学」という知識と社会の関係 |
2 |
|
|
|
|
| 第七回 ブルーノ・ラトゥールと |
2 |
| 『科学がつくられているとき』のもつ意味 |
|
|
|
| 第八回~第一五回 「科学がつくられているとき」の第一部までを発表 |
16 |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| 教科書 |
|
ブルーノ・ラトゥール『科学が作られているとき――人類学的考察』、川崎勝・高田紀代志(訳)、産業図書、1999年
|
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
今年度は、昨年以上に高度な翻訳文献を教科書として使用するため、議論に参加するには各自の予習復習が必須となる。発表担当箇所以外でも自ら文献を繙読でき、幅広い視野から議論に参加できることを目指す。
|
|
| 評価基準 |
|
成績評価は通常授業への貢献度で決定する。試験及びレポートは実施しない。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|