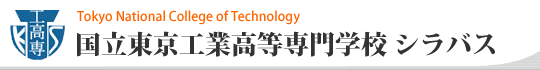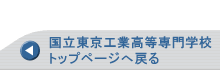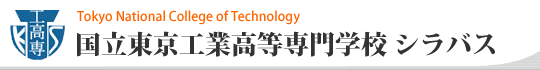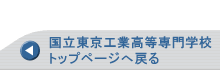| 1 実用法律学の導入 |
2 |
| 実用法律学の講義の全体像を紹介する。法と道徳の共通点と相違点を解説する。多様な観点から法を分類す |
|
| る。法の階層、憲法の最高法規性を説明する。基本的な法令用語を説明する。 |
|
|
2 |
| 2 憲法(1) |
|
| 日本国憲法の基本的人権の尊重を理解し、明治憲法と比較する。国民主権の内容を説明する。憲法の規定する |
|
| 基本的人権の種類と内容の概略を説明する。新しい人権に言及する。公共の福祉による人権の制約について説 |
|
| 明する。 |
2 |
|
|
| 3 憲法(2) |
|
| 日本国憲法の統治機構(国会・内閣・裁判所)を説明する。国会法、内閣法、裁判所法、国家行政組織法にも |
2 |
| 言及しながら、国会の位置づけ、立法過程、内閣の役割、司法権の独立について説明する。情報公開制法を説 |
|
| 明し、事例問題を検討する。 |
|
|
2 |
| 4 個人情報保護法 |
|
| 個人情報保護法制定の背景と関連法制を説明する。個人情報取扱事業者の義務を解説する。個人情報取扱事業 |
|
| 者に対する本人の権利を解説する。個人情報保護法に関連する事例問題を検討する。 |
|
|
2 |
| 5 行政法 |
|
| 国家資格、許認可、免許等の制度は、職業選択の自由・営業の自由を公益目的で規制している。このような観 |
|
| 点から、工業関連行政法規を例に取り上げ、その内容を考察する。国家公務員法や専門職に課せられる守秘義 |
2 |
| 務を確認する。ノーアクションレター制度について説明する。パブリックコメント制度について説明する。国 |
|
| 家賠償法における公務員の責任と国・地方公共団体の責任について考察する。 |
|
|
2 |
| 6 民事法(1) |
|
| 民法の基本原則を説明する。民法の全体図を説明する。民法総則における重要な事項(権利の主体・権利の客 |
|
| 体・法律行為・時効等)を説明する。物権と債権の相違について説明する。 |
|
|
|
| 7 民事法(2) |
|
| 債権の発生、消滅を説明する。契約の種類を説明する。債務不履行、不法行為、損害賠償請求を中心に説明す |
|
| る。製造物責任法の概略を説明する。従業者の責任と会社の責任について考察し、国家賠償法における場合と |
|
| 比較する。 |
|
|
|
| 8 刑事法 |
|
| 罪刑法定主義、犯罪の種類、犯罪の成立、刑罰の種類を説明する。捜査・逮捕・起訴等、刑事訴訟の概要につ |
|
| いて説明する。刑法以外の行政刑罰にも言及する。 |
|