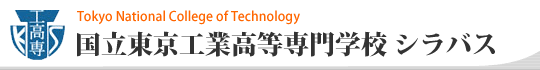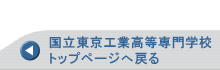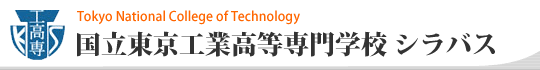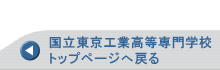| 授業の目標と概要 |
| 電気回路の基本的な考え方を学び、直流回路の計算ができるようになることを目標とする。導体の抵抗と温度の関係、 |
| 電流の発熱作用について理解する。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 電気・電子工学分野の基礎となる電気諸量の基礎的事項を理解し、電気回路の基本的な考え方を習得する。2年次に |
| 開講される電気電子序論II、及び電気回路Iが密接に関連する。3年次以降の電気回路II、電子回路I、電子回路IIの |
| 基礎となる科目である。 |
|
|
|
| 0. 本科目の概要説明 |
1 |
| 1. オームの法則 |
5 |
| ・オームの法則を用いて直流回路の電流、電圧、抵抗の計算ができる。 |
|
| ・電位の考え方を理解し、電位分布について習得する。 |
|
| 2. 直列・並列回路の計算 |
6 |
| ・直列接続と並列接続を理解する。 |
|
| ・直列、並列回路の合成抵抗が計算できる。 |
|
| ・分圧と分流、抵抗比について理解し、簡単な計算ができる。 |
|
| ・倍率器、分流器を学び、簡単な計測器の計算ができる。 |
|
| 3. ブリッジ回路 |
2 |
| ・ブリッジ回路の性質を理解し、ブリッジ回路を用いた未知抵抗の測定及び計算ができる。 |
|
|
|
|
|
|
| 4. キルヒホッフの法則 |
6 |
| ・キルヒホッフの第1法則と第2法則を理解し、回路方程式を立てることできる。 |
|
| ・キルヒホッフの法則による回路方程式を解き、解を計算することができる。 |
|
| 5. 重ねの理 |
4 |
| ・重ねの理を理解し、回路方程式を立てることができる。 |
|
| ・重ねの理を用いて、回路計算ができる。 |
|
| 6. 導体の抵抗 |
3 |
| ・抵抗率の考え方を理解し、導体のサイズと抵抗値との関係について計算ができる。 |
|
| ・抵抗温度係数の考え方を理解し、導体の抵抗と温度との関係について計算できる。 |
|
| 7. 電力とジュール熱 |
|
| ・直流回路の電力と電力量の計算ができる。 |
3 |
| ・電流の発熱作用及び熱-電変換を理解し、ジュール熱を計算することができる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
検定教科書 「電気基礎(上)」 宇都宮、高橋、和泉 (コロナ社)
|
|
| 補助教科書 |
|
「テキストブック電気回路」 本田 (日本理工出版会)
|
|
| 履修上の注意 |
|
1年次の代数I、代数II、幾何、物理、ものづくり基礎工学をよく復習しておくこと。
|
|
| 評価基準 |
|
教科書の演習問題が60%以上解けることを基準とする。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|