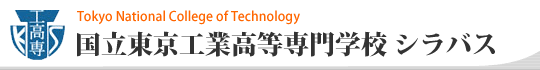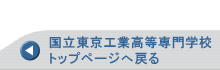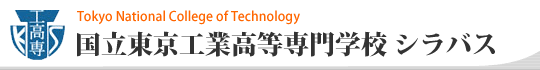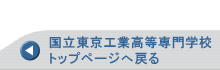| 授業の目標と概要 |
| 基礎的な電気回路の修得を目指して、交流を中心に共振回路、交流電力、相互誘導について、演習を交えて学習す |
| る。また一般的な回路に関する諸定理など電気回路Ⅰの内容を含む総合的な学習を行う。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 「電気回路Ⅰ」に続いて、交流回路の基礎を学ぶ。これは電子回路、回路網理論、伝送回路など電気回路の基礎とな |
| る。 |
|
|
|
| 「共振回路」 |
10 |
| 共振現象は、周波数選択や発信・増幅作用とも関連し、フィルタや各種測定系に広く利用されている。こ |
|
| のためつぎの項目について学ぶ。 |
|
| ・直列共振、並列共振、回路素子のQ、抵抗とリアクタンスの直並列等価変換、共振回路の構成 |
|
|
|
| 「交流電力」 |
4 |
| 交流電力の表現について、皮相電力、有効電力、無効電力、力率とその計算方法について学ぶ。さらに最 |
|
| 大供給電力の法則と整合について学ぶ。 |
|
| ・瞬時電力、平均電力 |
|
|
|
|
|
|
| 「相互誘導」 |
4 |
| 相互誘導は、2つのコイルがお互いに磁束を介して結合されている。このよな相互誘導回路の取り扱い、 |
|
| 計算方法について学ぶ。 |
|
| ・自己インダクタンスと相互インダクタンス、相互インダクタンスの正負、Mで結合された回路の等価回路 |
|
|
|
| 「直流回路の解き方」 |
|
| オームの法則は簡単な直並列回路の場合には有効であるが、複雑な回路の場合にはどうにもならない。こ |
10 |
| のような複雑な回路の解析にはキルヒホッフの法則が必要になってくる。 |
|
| ・キルヒホッフの法則、キルヒホッフの法則による回路の解き方、行列式、独立回路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
「テキストブック電気回路」(本田徳正著 日本理工出版会)
|
|
| 補助教科書 |
|
「わかる電気回路基礎演習」(光井・伊藤・海老原共著 日新出版)
|
|
| 履修上の注意 |
|
演習を中心に交流回路の総合的な学習をするので、電気回路Ⅰをよく理解しておくこと。また数学的背景として、複素数、三角関数、行列の取り扱いを復習しておくこと。
|
|
| 評価基準 |
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|