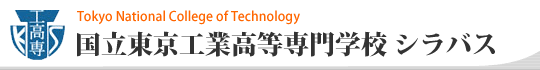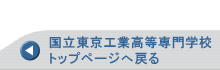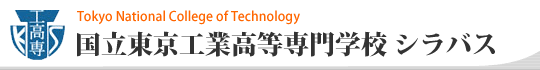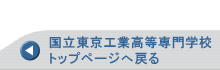| 1.プログラミング言語演習(北越,3回) |
| ・進化論的計算手法のサンプルプログラムを理解する。 |
| ・プログラムの修正,新たな関数の追加を行い探索効率の改善を試みる。 |
| ・得られた結果から手法の特徴,問題点について考察する。 |
|
| 2.プログラミング言語演習(松林,5回) |
| ・顧客の要望する仕様に合わせたプログラムを段階を追ってC言語で開発する。 |
| 具体的には,燃費計算ソフトを開発する。 |
| ・早く終わった学生は,難問集や懸賞問題を解く。 |
| (かつて,懸賞問題が満足に解けた学生はいない。) |
|
| 3.電子工作(田中, 7回) |
| 2つの課題から選択して、班単位での製作を行う。 |
| ・ガイダンス、仕様の説明、設計のヒント (4時間) |
| ・論理設計 (6時間) |
| 論理設計は2つの課題について個人で行う。論理回路図入力S/Wを用いて完成させる。 |
| ・実装図作成 (2時間) |
| 班単位で、製作課題を決めて、実際に製作する基板の実装図を作成する。 |
| 論理回路図と実装図をレポートとして提出する。 |
| ・基板製作 (10時間) |
| パーツリストを基に部品を集め、基板に半田付けにより配線作業を行う。 |
| ・動作検証 (6時間) |
| デバッグ、トラブルシューティングを行う。以上の一連の流れを通してもの作りの手順の理解。 |
| ドキュメントの必要性、品質の重要性の体験と理解を行う。 |
| *早く終了した班の拡張課題への挑戦 |
| A.点灯スピードを可変にする拡張 |
| B.当たり判定の拡張 |
| C.電子さいころの設計と製作 |
|
| 4.確率・統計演習(小嶋, 3回) |
| ・資料の整理および確率の計算に関する演習課題を行う。 |
|
| 5.コンピュータ計測制御(松林, 3回) |
| ・コンピュータ計測制御の授業内容に関する実験・演習を行う。 |
|
| 6.電子回路実験(西村, 7回) |
| ・オシロスコープによる波形測定 |