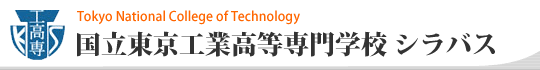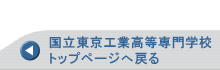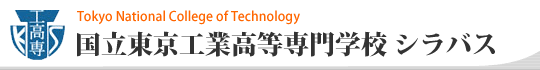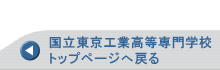| 授業の目標と概要 |
| 人間活動による環境への負荷を減らすため、多くの環境関連法令が定められている。この講義では、法令が制定され |
| る根拠となった生態学・生物学・化学の知識を法令と同時に学ぶことで条文の科学的理解と今後の技術者としての社 |
| 会生活を送る上で不可欠な知識の取得をめざす。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 分析化学・化学工学・環境科学と関連しており、生物学的知見を加えて環境の保護・管理の面から学習する。 |
|
|
|
| 1. 授業ガイダンス・環境関連法令概説 |
1 |
| 2. 水質汚濁概論<歴史・原因物質 |
2 |
| 主に水圏において発生した公害とその原因物質、また初回で概説した法令制定との関連について説明する |
|
| 3.生態系のつながりⅠ |
2 |
| 4.生態系のつながりⅡ |
2 |
| 大気は地球を取り囲み、全ての陸圏・水圏に接している。陸は川や河口を通じて海と連続しており、環境 |
|
| 問題はこれら相互の関連性無しには理解できない。主に水圏に関連する生態学について説明する。 |
2 |
| 5.水質汚濁および有害物質測定技術Ⅰ |
2 |
| 6.水質汚濁および有害物質測定技術Ⅱ |
|
| 水圏環境の維持・管理・回復には、汚濁および有害物質の性質を知り、その有無増減をモニターする必要 |
2 |
| がある。2回にわけて物質の性質と測定法を説明する。 |
|
| 7.水質汚濁の予測 |
|
|
|
|
| 8.汚水・有害物質処理技術Ⅰ |
2 |
| 9.汚水・有害物質処理技術Ⅱ |
2 |
| 汚染された水圏の回復に使われている技術を概説する。 |
|
| 10.大気汚染概論<歴史・原因物質 |
2 |
| 大気圏において発生した公害とその原因物質、また初回で概説した法令制定との関連について説明する |
|
| 11.生態系のつながりⅢ |
2 |
| 第3,4回と同様、主に大気圏環境に影響を与えるものについて説明する |
|
| 12.大気汚染測定技術 |
2 |
| 13.大気汚染および有害物質除去技術 |
2 |
| 14.大気汚染予測 |
2 |
|
|
| 15.環境問題を考える |
2 |
| 実際に現在進行形で様々な環境問題が起こっているが、玉石混交感もあり、かえって本質がわからなくな |
|
| りがちである。いくつかの最近の話題をピックアップして、本質および問題点、解決策などを議論する。 |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
各種科学技術と知見が中心であるが、常に関連する法令を意識すること。
|
|
| 評価基準 |
|
定期試験(全評価の4分の3)と授業内提出物点(全評価の4分の1)100点満点に換算した合計点で評価する。60点以上を合格とする。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|