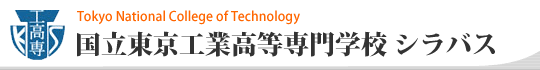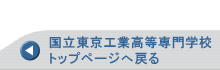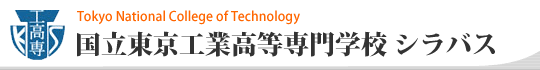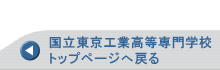| 授業の目標と概要 |
| 電子計算機Ⅰ、Ⅱの続きとして、CPU、メモリ、I/O等の周辺装置から成るマイクロコンピュータシステムの構造と作 |
| 製の実際について学ぶ。 |
| プログラム実行とマイクロコンピュータの内部動作、I/O動作の並列動作、さらには、マイクロコンピュータの使用に |
| 必要となる外部回路の設計について学ぶ。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 論理回路Ⅰ・Ⅱ、電子計算機Ⅰ・Ⅱ,オペレーティングシステムⅠを前提とし、CPUとI/O等の周辺装置の動作、並列 |
| 動作、プログラムを実行するマイクロコンピュータの構造と動作を理解し、マイクロコンピュータを用いたシステム |
| 設計の基礎を修得することを目標とする。 |
|
|
|
| 1.マイクロコンピュータの構造 |
11 |
| マイクロコンピュータの構成の概要と発展の経緯、ICとASIC、CPUの構造、各種レジスタの構成と役割、 |
|
| MCU、メモリと各種周辺機器、バスと信号、マルチタスク・各種割り込み・I/OとMCUの動作 |
|
| 2. アッセンブリ言語と機械語 |
4 |
| 言語の構造、アッセンブリ言語と機械語、アッセンブリ言語(機械語)の命令と信号及びMCUの動作、プロ |
|
| グラム設計の基礎、アドレッシング、マシンサイクルと評価 |
|
| 3. MPUの動作を確認するプログラムの作製 |
14 |
| Z80-SBC上を用いた、各種演算やレジスタ操作を伴うプログラムを作製動作させ、CPU・レジスタや周辺装 |
|
| 置の動き及びアッセンブリ言語(機械語)との関係を確認する |
|
| |
|
|
|
|
| 4. マイコンを使用した回路設計 |
15 |
| ハードウェア設計の基礎、ブロック構造とインタフェース、アクセス空間の概念・メモリの構造・アドレ |
|
| ッシングモードとメモリ操作、外部回路に関するプログラムの設計方法 |
|
| 5. マシンサイクルの実際及びI/Oデータチャネルの製作とLED表示装置の制御 |
8 |
| I/O装置のデータ転送を制御するI/Oデータチャネルプログラムを作製し、LED表示装置を動作させる。SBC |
|
| とオシロスコープを用いて、各信号線を測定し、マシンサイクル(信号の意味とタイミング)を実際に |
|
| 確認する。測定結果に基づいたソフトウェアタイマ、スキャン、I/Oマップ等を使用して、複数LEDを任意 |
|
| の時間間隔で並列に点灯させるプログラムを作製する。 |
|
| 6. 外部回路の設計 |
6 |
| MPUから制御する外部回路を設計する。まず、外部メモリを設計し、RAMが拡張されることを確認する。次 |
|
| に、メモリに書きこまれた値を表示するためのLED回路を設計し、MCP〜メモリ〜LEDが所定の動作をするこ |
|
| とを確認する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
著者:横田英一 書名:図解Z80の使い方 発行所:オーム社
プリント配布
|
|
| 補助教科書 |
|
著者:竹田 仰 書名:Z80シングルボードコンピュータの入門と実践
|
|
| 履修上の注意 |
|
実験付きの授業であり、全ての実験課題に報告書の提出が必要となる。指定期限内に提出のこと。
|
|
| 評価基準 |
|
グループで役割を持ち実験ができること。コンピュータの内部構造の基礎、マイクロコンピュータの動作原理、並列動作及びハードウェアとソフトウェアの役割が理解できること。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|