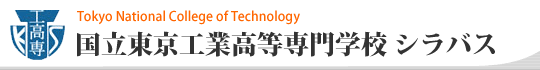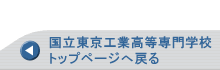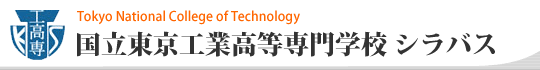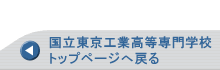| 授業の目標と概要 |
| 本講義では、集積回路設計に必要な基礎知識(集積回路の特徴、集積回路の種類、素子の基本的な性質、回路設計、 |
| 論理設計、レイアウト設計、故障診断など)の理解を目標とする。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 電気電子工学分野において、回路技術が基幹分野の1つとなっている。近年、多品種少量生産のASIC(Application |
| Specific IC)の需要が高まっているが、集積回路設計では、集積回路向けの設計技術の基礎を学習する。 |
|
|
|
| 1.集積回路の基礎 |
2 |
| 集積回路の特徴、分類方法、歴史について理解する。 |
|
|
|
| 2.集積回路の基本素子 |
3 |
| 集積回路の基本素子である抵抗、コンデンサ、バイポーラトランジスタ、MOSトランジスタの基本的な |
|
| 性質を理解する。 |
|
|
6 |
| 3.回路設計 |
|
| トランジスタ回路設計の概要、NMOS論理やCMOS論理のトランジスタ回路の回路方程式の解き方、トラン |
|
| ジスタ回路の設計手法、回路シミュレータの使い方を理解する。 |
|
|
|
| 4.論理設計 |
6 |
| 論理設計の概要、ゲートレベルの回路設計手法(PLA,FPGAなど)、論理合成ツールの使い方を理解する。 |
|
|
|
| 5.レイアウト設計 |
6 |
| レイアウト設計の概要、制限付きチャネル配線手法を理解する。 |
|
|
|
| 6.故障診断 |
6 |
| 論理回路の故障診断の概要を理解する。 |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
デジタル回路の基礎知識、C言語などの高級言語の基礎知識を修得していること。
|
|
| 評価基準 |
|
規模の大きなデジタル集積回路の設計手法を修得する。100〜500ゲート規模のデジタル集積回路の設計ができる。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|