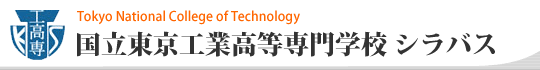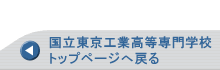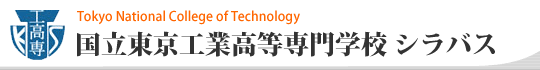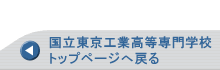| 1.金属材料の変形と塑性力学の基礎 1.1弾性、塑性、破断 1.2転位 1.3応力-ひずみ曲線 1.4降伏条件 |
2 |
| 2.塑性加工応用製品 |
2 |
| 2.1身の回り製品に使われている塑性加工 アルミ箔、なべ、スプーン、飲用缶 |
|
| 2.2建築土木に使われている塑性加工 サッシ、鉄筋、H形鋼 |
|
| 2.3自動車、家電に使われている塑性加工 自動車ボディ、ICリードフレーム、ノートPC筐体 |
4 |
| 3.塑性加工材料と工具材料 3.1鉄鋼と熱処理 3.2加工硬化 3.3回復と再結晶 3.4材料強化機構 3.5炭素鋼 |
|
| 3.6アルミニウム合金 3.7マグネシウム合金 3.8チタン合金 |
2 |
| 4.圧延加工 4.1圧延の原理 4.2板圧延 4.3棒・線・形・管の圧延 |
2 |
| 5.押出し 5.1前方押出し 5.2後方押出し 5.3押出しによる管材の製造 |
1 |
| 6.引抜き加工 6.1伸線機 6.2引抜ダイス 6.3ダイスレス引抜 6.4線材 6.5引抜き荷重 |
1 |
| 7.プレス機械 7.1プレス機械の構造 7.2プレス能力 |
2 |
| 8.せん断加工 8.1せん断加工の原理 8.2せん断切口面 8.3せん断金型 8.4精密せん断 |
2 |
| 9.曲げ加工 9.1曲げと鞍型変形 9.2スプリングバック 9.3ロール曲げ 9.4管の曲げ 9.5パイプベンダー |
|
| 10.絞り加工 10.1絞り加工の原理 10.2絞り加工における各部の応力状態(縮みフランジ、伸びフランジ) |
2 |
| 10.3クリアランス、パンチ肩半径、ダイ肩半径、しわ押さえ 10.4絞り限界、絞り力 |
5 |
| 11.鍛造 11.1自由鍛造 11.2熱間鍛造 11.3冷間鍛造 11.4密閉型鍛造 11.5コイニング、エンボス成形 |
2 |
| 12.金型 12.1金型の種類と構造 12.2単発金型 12.3順送金型 トランスファー金型 |
|
| 13.最近の塑性加工技術 13.1ファインブランキング 13.2ハイドロフォーミング 13.3インクリメンタル |
2 |
| 13.4有限要素法解析技術 |
|
| 14.金型に関するプレゼンテーション |
|