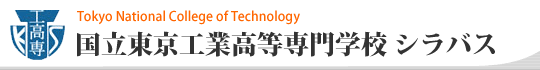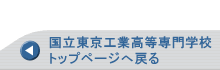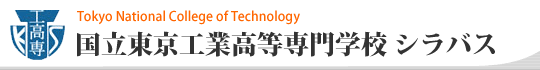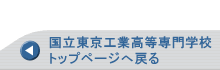| 授業の目標と概要 |
| 自動制御の発展により家庭から産業界まで自動化、省力化が進められている。授業では前半で物理現象の数学モデル |
| 化,微分方程式のラプラス変換による解法を復習する。そしてモータの位置決め制御を例として取り上げ,古典制御 |
| 理論の復習を行なう。倒立振り子を例として取り上げ,極配置法による制御を現代制御理論のアプローチについて学 |
| ぶ。 |
| またフィードフォワード制御の例として,管内能動消音について解説する。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 共通専門科目であり,微分方程式・ラプラス変換を学んでいない学生も対象になっている。 |
| 本校準学士課程のラプラス変換および,微分方程式で記述された物理現象の扱いからスタートし,同じく準学士課程 |
| の制御工学を定着させ,現代制御理論へのアプローチを行なう位置づけとなる。 |
|
|
|
| 1.自動制御とは |
2 |
| 自動制御の種類と発展過程 |
|
| 2.数学的準備 |
2 |
| 定係数線形微分方程式,ラプラス変換,ラプラス変換による定係数線形微分方程式の解, |
|
| 行列,行列の固有値・固有ベクトル,運動方程式 |
|
| 3.物理現象の記述と状態量 |
4 |
| 代表的物理量 |
|
| 運動方程式 |
|
| キルヒホフの定理 |
|
| 4.基本的なフィードバック制御 |
5 |
| 伝達関数とs領域で入出力 |
|
| フィードバックを用いたモータの位置決め制御 |
|
| 5.現代制御のアプローチ |
6 |
| 状態量,状態空間の扱い |
|
| 状態方程式と解法 |
|
| 状態推移行列 |
|
| 可制御性と可観測性 |
|
| 4.倒立振り子を例にとった制御方法 |
6 |
| 状態方程式 |
|
| 可制御性,可観測性 |
|
| 状態フィードバックによる制御系の設計(極配置法) |
|
| (最適レギュレータ) |
|
| 5.能動消音の紹介 |
4 |
| 実機による演習 |
|
| フィードフォワード制御 |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
プリントを配布します
http://tokyo-ct.net/usr/kosaka/index.htmlの授業資料参照
|
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
複素数,物理(剛体の力学),電気工学,線形定係数微分方程式,ラプラス変換,線形代数(固有値,固有ベクトル)の知識を復習しながら使います。
|
|
| 評価基準 |
|
古典制御によるモータの位置決め制御の解析がわかること。状態方程式を用いた解析がわかること。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|