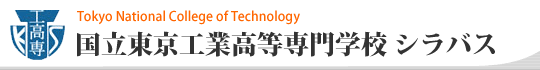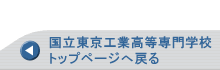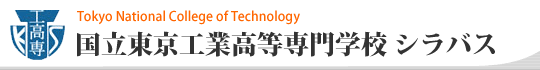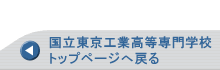| 増幅回路の仕組み、演算増幅回路の基礎を理解する。 |
| (5)電波と通信のしくみ |
| ラジオ放送の仕組みを学び、電波の性質を理解する。 |
| (6)光エレクトロニクス |
| ものづくり体験や光通信実験を通じ、光エレクトロニクスの基礎を学ぶ。 |
|
| 【情報工学分野】 |
| コンピュータグラフィックス(CG)及びマイクロコンピュータ(マイコン)を題材としたプログラミング入門を行 |
| う。プログラムを通じた様々なものづくりを体験すると共に、プログラミング一般に通じる考え方を修得する。 |
| (1)音の波形と分析 |
| 実際に録音した音の波形やスペクトルの観測と測定を通じて、信号処理の一端に触れる。 |
| (2)プログラミングの基本 |
| CGを題材として、プログラミングの基本となる考え方について学ぶ。 |
| (3)変数の利用と繰り返し |
| 変数と繰り返しを用いたCGのプログラムを作成し、プログラミングに特有な考え方を学ぶ。 |
| (4)動きのあるグラフィックス |
| 条件判断と変数の高度な利用により、動きのあるCGのプログラムを作成する。 |
| (5)表示装置とスイッチの利用 |
| マイコンを用いて、組込機器用のプログラミングを体験する。 |
| (6)センサの利用とモータの制御 |
| ロボコンを想定して、モータを制御するプログラミングを体験する。 |
|
| 【物質工学分野】 |
| 基本的な化学的知識や考え方を理解するために、物質の生成、化学反応を体験する。また日常生活にも化学が密接に |
| 結びついていることを実験を通して理解し、その原理を追求する。 |
| (1)物質の分離と精製 |
| 基礎的な実験器具の使い方を学ぶ。ろ過、蒸留、再結晶、抽出などの実験を行う。 |
| (2)物質の変化と反応 |
| 液体窒素を使って物質の状態変化を体験する。また金属が関係する化学変化を観察する。 |
| (3)コンピュータ化学/化学変化の量的関係と反応熱 |
| コンピュータを使って分子モデリングや食物連鎖のシミュレーションを行う。また反応熱を測定し、ヘスの法則を |
| 学ぶ。 |
| (4)酸塩基と中和反応 |
| pHに関する簡単な実験を行う。中和滴定により酸の濃度を求めたり、滴定曲線を作成する。 |
| (5)酸化還元反応 |
| 金属樹、燃料電池などの酸化還元反応を体験する。また滴定により溶液中のビタミンCの定量を行う。 |
| (6)その他、応用的な実験 |
| ナイロンの合成、金属イオンの定性分析、電気分解などを行う。 |
|
| |
| |
| |
| |