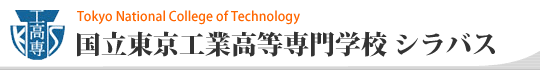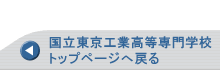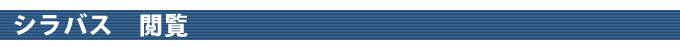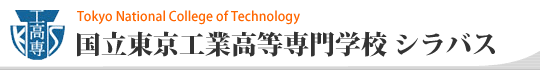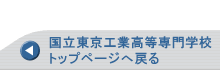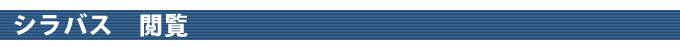| 授業の目標と概要 |
| 情報の発生処理・通信・記憶に関してシステム的にとらえ、システム構成法と利用者が実感する処理システムの処理速度・性能及 |
| びネットワークの通信品質との関係について学習する。情報システムに関しては、利用者が感じる処理速度やシステム性能に大き |
| く影響を与えるため、各種処理システム及びネットワーク等の構成の特性を知ることが極めて重要である。 |
| 授業は輪講形式で行う。事前に、各々が割り当てられた範囲の調査などを行い、配布する資料などを作成した上で説明を行う。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 情報やネットワークの品質、信頼性や安全性という視点からの学習を行う。また、自ら最新動向などの調査を行う事により、情報 |
| 収集能力を高めるとともに、プレゼンテーション能力の向上のはかる。 |
|
|
|
| 1.インターネットの高速化と関連技術 |
10 |
| インターネットの利用状況と役割、その重要性について理解する。 |
|
| また、SONET/SDH、ATM、WDM、ギガビットイーサネット等の方式を理解する。 |
|
|
|
| 2.インターネットの通信品質と制御 |
|
| 2.1.通信品質測定技術 |
10 |
| インターネットにおける通信量、通信品質の受動的測定法、能動的測定法について理解する。 |
|
|
|
| 2.2.通信品質アーキテクチャ |
|
| 帯域割り当て、RSVP、リーキーパケットアルゴリズム等について理解する。 |
|
|
|
| 2.3.サービス差別化のためのアーキテクチャ |
|
| サービス種別に応じた優先制御の方法について理解する。 |
|
|
|
| 2.4.ネットワーク層制御の高速化 |
|
| 各種の輻輳制御法について理解する。 |
|
|
|
| 3.信頼性と安全性 |
|
| セキュリティポリシ、暗号化技術、認証技術等について理解する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| 教科書 |
|
尾家 祐 他:”社会基盤としてのインターネット”、岩波書店
|
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
指定された日時までに、割り振られた範囲の調査を行い、配布物などの準備を行った後に発表(講義)を行う。準備不足で講義が行えないようなことにならないよう、余裕を持って準備を行う事。また、発表の直後、速やかにその範囲のレポートを提出する。
|
|
| 評価基準 |
|
プレゼンテーションの評価は、準備状況、理解度と発表内容によって行う。
レポートの評価は、調査内容と理解度、まとめ方などによって行う。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|