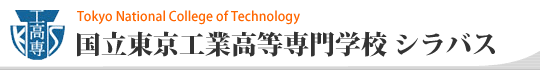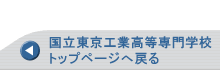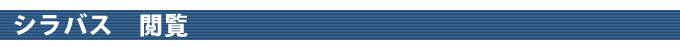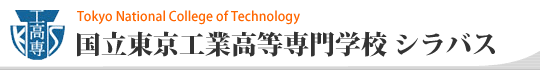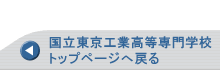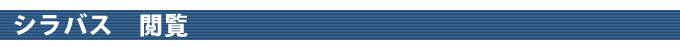| ・黒崎茂「材料強度解析学」 |
| ①実際の構造部材の破壊事例から,どのような形状のき裂から破壊が起きたか調べる。②その破壊前のき裂か |
| ら,どのようにモデル化するかを考える。③モデル化したき裂の応力拡大係数を「K値ハンドブック」を使い |
| 求める。 |
| ・木村南「接合工学」 |
| 溶接,はんだ付け,半導体実装,接着,かしめ,ねじ締結などの接合技術について,最近の製品事例を課題と |
| して与え,接合強度計算,使用寿命,分離・解体性,リサイクル性についてまで演習する。 |
| ・福田勝己「精密機械工学」 |
| 精密機械工学、特にマイクロ・ナノテクノロジーの基盤技術であるトライボロジーを中心に,その基礎事項を |
| 習得するために,国内外の論文等を題材に輪講を実施する。 |
| ・斉藤純夫「流体工学」 |
| 流体機械に使われる翼型の幾何学的形状と特性との基本的関係を理解するため,国内外の論文等を題材に演習 |
| を行う。 |
| ・下井信浩「ロボット工学」 |
| 最新のロボット技術を研究して,機構・制御・センサ技術の3項目構成されているロボットの基本技術等につ |
| いて演習を実施する。 |
| ・清水昭博「計測工学」 |
| 測定値の不確かさ解析についての計測工学関係の文献を用いて,輪講によってその内容を理解し,学生個人が |
| 興味を持つ問題に実際に適用してみる演習を実施する。 |
| ・筒井健太郎「熱工学」 |
| 伝熱工学における熱移動の式の多くは,物理現象による基礎式と多くの実験に基づいて作成されている。本演 |
| 習では物理的な現象の理解に基づいた各種式の理解と工学への応用を目的とする。 |
| ・多羅尾進「運動シミュレーション」 |
| ロボット等多体系の動力学解析について,その基本事項を学ぶために,国内外の論文等を題材に演習を行う。 |
| いくつかのモデルについて,実際に動力学計算を行う。 |
| ・青野正宏「情報通信工学」 |
| コンピュータネットワークやパーソナル通信などを中心に技術的課題を与えて解決策を探る演習と海外文献に |
| よる最近の動向調査を輪講により行なう。 |
| ・小坂敏文「制御情報工学」 |
| 制御工学と情報工学を融和させ,音響信号,画像信号をもとにフィードバック量を生成し,機構を制御するシ |
| ステムの実装を行なう。 |
| ・横山繁盛「高性能マイクロプロセッサの利用技術」 |
| 最近の高性能マイクロプロセッサのアーキテクチャについて文献による調査をおこない,高性能ハードウェア |
| を生かすためのプログラミング技術の習得をおこなう。 |
| ・鈴木雅人「手書き文字認識における識別関数の設計」 |
| 手書き文字認識を例として、統計的な手法に基づくパタン認識論のうち、特に高次元確率空間における識別理 |
| 論について学習し,識別アルゴリズムの実装を行う。 |