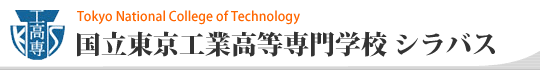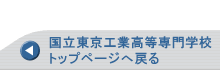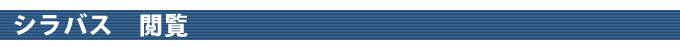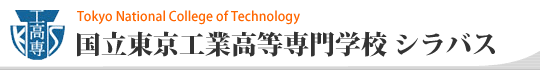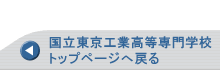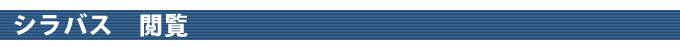| 授業の目標と概要 |
| コンピュータシステムにおいて重要な役割を果たしている各種情報装置の機能を、その構造や特性を学ぶことにより |
| 理 |
| 解する。メモリ装置や2次記憶ストレージ装置の物理的特性に基づいたコンピュータアーキテクチャにおけるI/Oサブ |
| システムの観点からシステム的な構築法を学ぶ。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 選択科目の計算機アーキテクチャと関連する科目である。 |
|
|
|
| 1.情報装置の位置付け |
2 |
| 歴史的発展の経緯とコンピュータシステムの中での位置付け |
|
|
|
| 2.各種情報装置概論 |
|
| 主記憶装置、補助記憶(ストレージ)装置の構造と特性 |
4 |
| 各種入力装置、出力装置 |
|
|
|
| 3.メモリ構成法 |
|
| 半導体メモリ、磁気ディスクの特性 |
|
| それらを基にしたコンピュータシステム内の構成法 |
|
| (外書輪講形式で行い、レポート提出) |
8 |
|
|
| 4.I/Oサブシステム構成法 |
|
| I/Oサブシステムの位置付け |
|
| プログラムドI/O方式とI/O割り込み方式 |
|
| I/OプロセッサとI/Oチャネル、DMA方式 |
5 |
| 入出力命令とCCW(チャネルコマンドワード) |
|
| (外書輪講形式で行い、レポート提出) |
|
|
7 |
| 5.最新のメモリ、ストレージ技術 |
|
| DRAM技術の進化と高速化手法、 |
|
| 不揮発メモリ技術、ストレージ技術の大容量化と高速化 |
|
| それらがコンピュータアーキテクチャにもたらすもの |
3 |
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
著者:青木恭太 書名:計算機システムの周辺装置 発行所:近代科学社
著者:Kai Hwang 書名:Computer Architecture and Parallel Processing
|
|
| 補助教科書 |
|
著者:John P.Hayes 書名:Computer Architecture and Organization
|
|
| 履修上の注意 |
|
授業の一部を外書輪講による発表形式で行い、レポート提出を行う。
それらを評価点に加える。
|
|
| 評価基準 |
|
コンピュータシステムの中における各種情報装置の特性、メモリを中心としたI/Oサブシステムの関連及びその機能について、英語のテキストを読解することにより理解する。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|