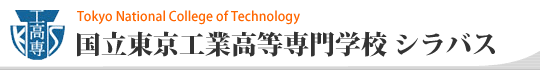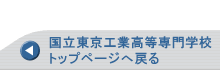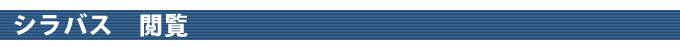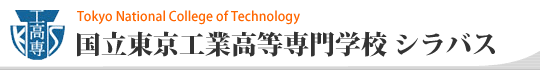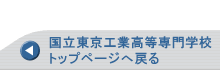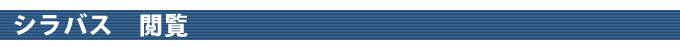| 授業の目標と概要 |
| 化学は物質を直接取り扱う学問として自然科学の基礎であり、分析化学はその物質を定性・定量する学問として化 |
| 学の基礎を成している。この分野は化学分析と機器分析に大別され、理論および方法の研究を含む。本授業では溶液 |
| 内平衡をはじめとする化学分析法の基礎、化学操作の意味を理論的に理解できることを目標とする。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 既に学習内容と関連する実験を2年次の分析化学実験で行った。本授業はそれらを理論的に理解するためのもの |
| であり、物理化学と関連する。 |
|
|
|
| 1.溶媒としての水、溶液の濃度 水の性質、モル濃度、その他の濃度 |
2 |
|
|
| 2.化学反応と化学平衡 活量、熱力学的平衡定数、濃度平衡定数 |
2 |
|
|
| 3.酸・塩基の概念 プロトン供与体・受容体、共役酸・塩基 |
2 |
|
|
| 4.水溶液における酸・塩基反応 酸解離定数、塩基解離定数 |
2 |
|
|
| 5.pHの計算 強酸、強塩基、弱酸、弱塩基の各水溶液 |
2 |
| 塩の加水分解 |
|
|
2 |
| 6.pH緩衝液 弱塩基+その塩、弱酸+その塩 |
|
| |
|
| 7.酸塩基滴定 滴定曲線、酸塩基指示薬 |
2 |
| |
|
|
|
|
| 8.項目1〜7の重点確認 前期中間試験の解説 |
1 |
| |
|
| 9.金属錯体の構造と錯体の安定度 錯体とは。Lewisの酸・塩基とHSAB則 |
2 |
| |
|
| 10.錯体生成反応の平衡論 錯体の生成定数(安定度定数)、キレート |
2 |
|
|
| 11.副反応 副反応係数と条件生成定数、マスキング剤 |
2 |
|
|
| 12.キレート滴定(1) 滴定曲線、金属指示薬 |
2 |
|
|
| 13.キレート滴定(2) 代表的な滴定法 |
2 |
|
|
| 14.沈殿生成・沈殿溶解の平衡 溶解度積とイオン積、沈殿の溶解平衡モデル |
2 |
|
|
| 15.沈殿分離 分別沈殿 |
2 |
|
|
|
|
|
| 16.項目9〜15の重点確認 前期末試験の解説 |
1 |
| |
|
| 17.沈殿の形成過程 過飽和度、均一沈殿法、沈殿の汚染 |
2 |
| |
|
|