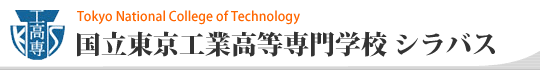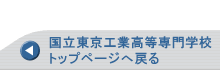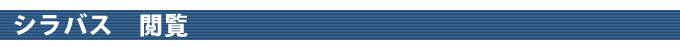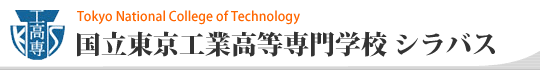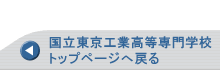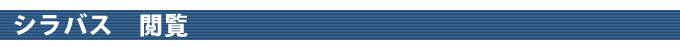| (卒業研究そのものは第5学年の教科であるが、研究室配属のための作業は第4学年の終わりに実施している) |
|
| 1.研究室への配属 |
|
| 1月、「研究室及び卒業研究案内」の冊子を、第4学年学生に配布する。これには、各研究室の研究内容と卒業研究 |
| の内容が、簡潔に紹介されている。学生は、この冊子を参考にして、自分が興味を持つ分野に関係ある研究室を知る |
| ことができる。 |
|
| 2月、卒業研究を担当する教員が、個々に、4年生のクラスに対して、卒業研究に関する説明を口頭でおこなう。4 |
| 年生は、この機会を利用する、あるいは別途、各研究室を訪問するなどして、研究室及び卒業研究に対する理解を深 |
| めておく。 |
|
| 3月、配属の決定。「研究室及び卒業研究案内」の冊子には、「研究室配属希望調査票」が添付されている。学生 |
| は、指定された方法で、希望する研究室名を記入し、卒業研究発表会終了時に、学級指導教員に提出する。研究室へ |
| の配属は、学科会議で決められ、第4学年の学年末までに、学級指導教員から発表される。 |
|
| 2.卒業研究中間発表 |
|
| 9月前半に、卒業研究中間発表をおこなう。発表に先立ち、発表要旨(電気工学科所定の書式)を学級指導教員に提 |
| 出し、その指導のもとに要旨集を作成する。(発表会には第4学年学生も出席し、討論に参加するとともに、各研究 |
| 室の研究内容を知る機会とする。) |
|
| 3.卒業研究発表会 |
|
| 3月初めに、卒業研究発表会において、卒業研究の成果を発表する。この発表会は、研究の内容とともに、発表の仕 |
| 方も評価する。発表内容と発表技術を含めた、事前の準備が必要である。 |
|
| 2月下旬、卒業研究発表要旨(電気工学科所定の書式)を学級指導教員に提出する。 |
| 3月初旬、卒業研究発表会において、発表する。 |
|
| 4.卒業論文 |
|
| 卒業研究の成果をまとめた卒業論文を、2月下旬の所定日までに、電気工学科長に提出する。 |
|
| 卒業論文の書き方については、年度当初に、学級指導教員から配布される「卒業研究の書き方」などを参考にする。 |
| 卒業論文の表紙は、電気工学科所定の書式に従って作成する。 |
|