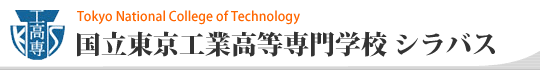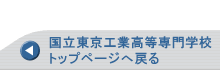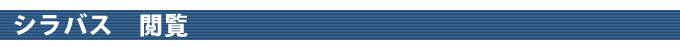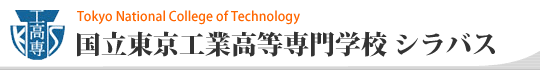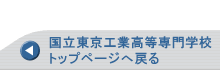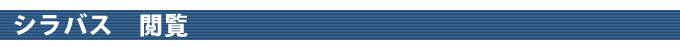| 授業の目標と概要 |
| 無線通信方式では,伝えるべき信号をそのままの形で空中に放射することはせず,一般に信号の変調を行なう。本科 |
| 目では,アナログ・ディジタル信号の各種変調方式について理解することを目的とする。また,通信の物理層に関す |
| る基本事項や多重アクセス方式,近年実用化が進んできたスペクトル拡散通信方式・超広帯域通信の概要について学 |
| 習する。 |
|
| カリキュラムにおける位置づけ |
| 三角関数の演算,確率・統計で学んだ正規分布の性質などについて復習しておくこと。同時開講の応用数学Ⅰで学ぶ |
| フーリエ変換や情報数学Ⅱで学ぶ有限体に基づく系列生成などの知識が関連深いので,これらを総合的に学ぶ姿勢で |
| 臨むこと。本授業で扱う内容は無線通信が主であるが,内容の一部は情報通信工学Ⅱ・Ⅲなどで学ぶ有線通信とも関 |
| 連深い。また,本授業では,OSI参照モデルの物理層に関する内容を多く扱うことになる。 |
|
|
|
| 1.情報通信工学の基礎 |
8 |
| 1.1 通信媒体と基本技術 |
|
| ・有線通信 ・無線通信 ・ケーブルの種類 ・伝送路符号 |
|
| 1.2 無線通信と信号の変復調 |
|
| ・電磁波とその性質 ・マクスウェルの方程式 ・周波数帯域とその利用 ・信号とその表現 |
|
| ・周波数 ・波長 ・電磁波の速度 ・変調と復調 ・アナログ変調 ・ディジタル変調 |
|
| 1.3 伝送特性と評価法 |
|
| ・情報量 ・情報伝送速度 ・S/N 比 ・信号のスペクトル |
|
| 2.アナログ変調方式 |
4 |
| ・振幅変調 ・周波数変調と位相変調 ・AMとFMのS/N比 |
|
| 3.パルス変調方式とパルス符号化変調 |
2 |
|
|
|
| 4.ディジタル変調方式 |
8 |
| 4.1 ディジタル変復調の原理と特性評価 |
|
| ・ディジタル通信の受信誤り ・ビット誤り率 ・通信路容量 ・Eb/N0比 ・周波数利用効率 |
|
| 4.2 相関関数とフィルタ |
|
| ・復調の原理 ・低域通過フィルタ ・相関関数 ・整合フィルタ |
|
| 4.3 さまざまなディジタル変調方式 |
|
| ・ASK ・FSK ・BPSK ・多値変調 ・QPSKの変復調 ・m値QAM |
|
| 5.多重アクセスとスペクトル拡散通信 |
6 |
| 5.1 ワイヤレス通信の仕組みと諸問題 |
|
| ・チャネル間干渉 ・マルチパス ・セルラ通信方式 ・遠近問題 ・ハンドオーバ |
|
| 5.2 多重アクセス方式 |
|
| ・TDMA ・FDMA ・CDMA ・OFDM |
|
| 5.3 スペクトル拡散方式と系列設計 |
|
| ・スペクトル拡散変調 ・直接拡散方式 ・さまざまな拡散系列 ・広帯域通信とその応用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
| 補助教科書 |
|
| 履修上の注意 |
|
原則として授業の最後に問題演習を行なう。演習の解答は提出を求めるので,毎回A4のレポート用紙および電卓を用意すること。必要に応じて,方眼紙を用意すること。
|
|
| 評価基準 |
|
各種アナログおよびディジタル変調方式やその性質の違い,多重アクセス技術やスペクトル拡散通信方式の原理について理解し,無線通信の利用実態を把握する。
|
|
| 評価法 |
|
| 学習・教育目標 |
東京高専 |
|
JABEE |
|